人文社会学科社会学コース 三部倫子(社会学)
- 研究
日常に潜むジェンダーとセクシュアリティ
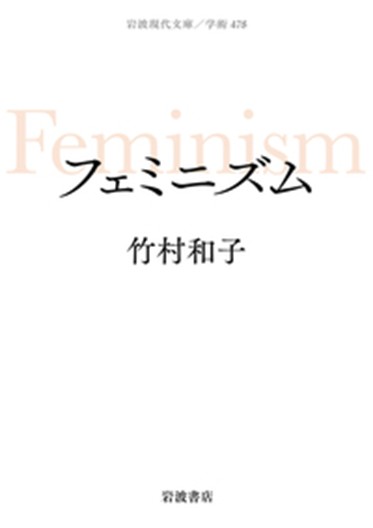
「女らしさ」「男らしさ」って何だろう。「女(男)らしくしなさい!」と叱られると嫌な気持ちにさせられた。一方で、「女(男)らしいね」と褒められてまんざらではなかったりする。でも、誰を好きになるのか、どういう風に好きになるのかも、なんだか「普通」と「普通じゃない」があるみたい。誰がその「普通」に入っているのだろうか。そもそも、人を好きにならないとだめなのかな。「普通」って何!?
みなさんは、多かれ少なかれこうした経験や疑問を抱いた事があるのではないでしょうか。誰にとっても身近で時にはまとまりついて離れないジェンダーやセクシュアリティの研究は、「なんかおかしい」という人の違和感からはじまりました。
常に現場から ジェンダー・セクシュアリティ研究
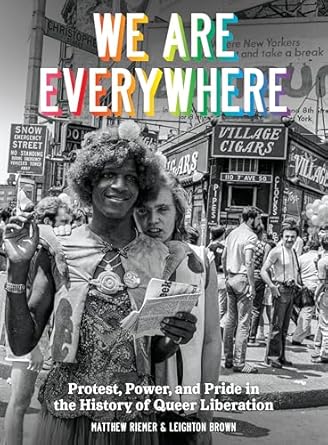
「女性が投票できないのはおかしい。それは差別だ!」「性的対象にされるのはおかしい!それは性暴力だ!」という怒りと、その怒声に紛れる確かな声(異性愛ではない人、男女の性別にあてはまらない人からのそれ)、例えば「同性と結婚できないのはおかしい!」(「でもそもそも結婚しないとだめなの?」)とともに発展したフェミニズム、レズビアン・ゲイスタディーズ、その後のクィア研究は、特定の学問分野を指しているわけではありません。
文学、文化人類学、心理学、社会学などの領域にまたがっている(それだけ研究しがいがあるということ)テーマについて、私は社会学を足場に考えることを選びました。社会をつくる人に率直に興味をもったこと、そして、「プライベートなんだから秘匿すべき」とされがちな性や女(男)らしさの経験は、個人的なものではなく社会的なものじゃないかと直感的に感じたからです。
社会学を足場に質的調査
社会学は人と人との間の相互行為を対象に、様々なアプローチでその対象に迫ります。既存の文献から得られた知見から考えを深めることもあれば、人々の主観的な意味づけを聞き取るインタビューをしたり、実際の相互行為の現場に身を置いて観察したりします(こうした方法を「質的調査」といいます)。
人々にとって当たり前となっている(だからこそ秩序が維持/されたように見える/相互行為が可能となる)実践は、意識しないと記録もされず、他の知るところになりません。相手と信頼関係を築き、時に自分もそこのメンバーとなって、ジェンダー・セクシュアリティの規範が凝縮される「家族」をテーマに質的調査を用いて、研究を行ってきました。
「家族」って何だろう

「家族」という身近な存在のなかでなきものとされたり、抑圧されてきた現象として、親と子の間で生じるカミングアウトの経験をとりあげたのが研究者としてのスタートでした。
次世代再生産を期待される子どもの、親への理解を求める葛藤と、自己のセクシュアリティを見つめ直す親、ユーモアでカミングアウトの困難を乗り越えようとするセルフヘルプグループの実践を明らかにしてきました。その後、異性愛や性別二元論を中心とする家族のなかで生きてきた人たちが、それとは異なりうる親密な関係性を、どのように創っているのかを問うために、同性カップルの子育てに関するインタビュー調査も行いました。
よりより看護と医療を目指して
最近はこうした「家族」研究で浮上した社会学的課題が、看護や医療の領域に移った際にどのような形で「問題」として生じるのかに興味を持っています。看護・医療専門職と協働しながら、医療格差や差別を減らすために社会学者として貢献していきたいと考えています。