日本アジア言語文化学コース 尾山慎(国語学)
- 研究
日本語の文字表記
日本語は、漢字・平仮名・片仮名・アルファベット・アラビア数字をまぜて使う。「2時からNHKでバスケの試合見よう」などは、何の変哲もない文章だが、こんな短い文章で5種類も同時に使うのは現在、世界広しといえども日本だけだ。
最初からそうだったわけではない。日本語にはもともと文字はなかった。中国の漢字と接し、これを取り入れたのである。単に書くときは漢文(中国語)で書くようにしたのみならず、日本語を書くための道具として改造を施した。だから、かつての日本語にはいくつも書き方があり、文章の内容によってそれらを変えていた。
音読みと訓読み

漢文を訓読することで音読みと訓読みが発生した。今度はその音読みや訓読みをつかって、日本語を書くことができるようになっていく。万葉集に「いまだ渡らぬ」という表現がでてくるが、それを「未渡」と書いている。
それはつまり、「未」を「イマダ~ズ」と読んでいた証拠だ。読めるから書けるようになる。そして、書くことを繰り返して、読みが確定していく。私たちがいま、音読み/訓読みとして義務教育で習うのは、先人たちが漢字と格闘し、そしてわが物としてきた、その年輪のようなものだ。
平仮名・片仮名
平安時代には平仮名や片仮名が発生した。面白いのは、平仮名や片仮名ができても、漢字を棄てなかったという点だ。混交させたり、文章の種類によって切り替えたりするという多様な書き方を選んだのだ。
また漢文も、日本語の語順にしたような「変体漢文」として亜流を生み出したりして、目的に応じて、それらを使い分けていた。もし現代に例えるなら、公文書が漢字のみ、公文書に準じるものや手紙は漢字と仮名の交じり、歌や物語はおおむね平仮名だけといった具合だ。これが、どのように混交したり、合流したりして、現代にいたるのか。謎はまだまだ尽きない。
黎明期の研究
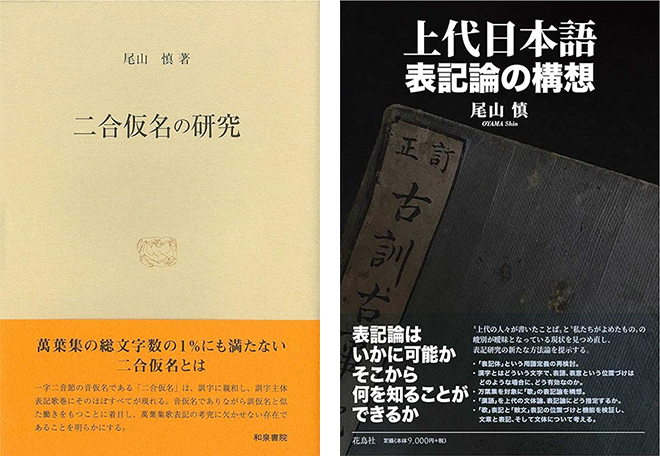
古代日本──日本語の、かくも魅力的な文字表記の仕組みを研究するなら、その始まりの世界へ。そう思って研究を始めた。奈良時代以前はまだ漢字しかない時代。やはり、音読み訓読みを駆使する。
一字で二音、なんと三音を表わす当て字もある(船の「いかり」に感情の「慍」(いかり)を当てる)。本当にさまざまな試行錯誤がそこにはある。同時に、後々、日本語表記に用いられる方法の、そのほとんどは、実は奈良時代以前にもう試されていることがわかった。
こういった探索、検証、考察を経て、これまで刊行した研究書としては、万葉仮名の多様さと創意工夫を研究した『二合仮名の研究』、そして、漢字のみで日本語を書くことを模索した時代、それを現代の私たちがどうやって研究できるかということ自体から考えた『上代日本語表記論の構想』がある。これらの研究を通して、日本人が漢字とどう付き合って、自分たちの言葉を書く方法を獲得、確立していったかが見えてきた。
![]()
万葉集「泣きなむ」の当て字。訓読みの当て字で、そもそも訓読みが定着していないとこんなことはできない。
表記の多様性研究
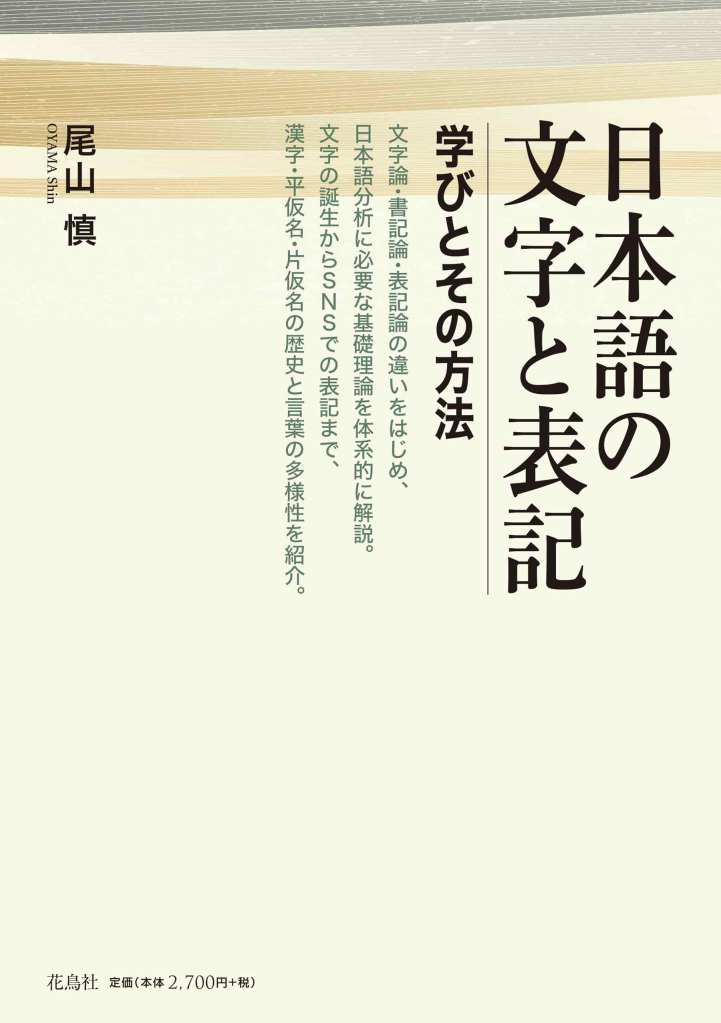
表現手段としての文字表記──私は、上記のコアな古代日本語研究をさらに覆うこととして、広く、日本語が文字の使い分けも表現手段と考えているところに、時代を問わず興味を持って研究している。
「日差し」と「陽射し」では暑さが違うように思える。「熊」「くま」「クマ」と書けるが、学術名は片仮名と決まっている。文字がいろいろあるので、それを利用して表現や理解、分類の助けにしているのである。フリガナを振ればなおさら世界は広がる。震災復興への尽力を謳ったポスターには「宮城は現在(いま)も現実(いま)に立ち向かう」とあった。一文なのに、二重の意味や、補助線のように理解を促したりできるのだ。
いまから二千数百年前、ギリシアの時代から、文字は音声の付属品、二の次のような扱いをうけてきた。言語学者ソシュールは「召使い」と譬えたが、日本語の文字表記は、召使いどころか、音声の言葉を華麗に彩るたと主役でさえ、ある。この研究は、日本だけに閉じこもるものではなく、その独自性が結局は世界を見渡してこそよくわかってくる、それが面白くて、研究している。上記2冊の研究書を受けて、日本語の文字・表記を総括的に概論した一冊が『日本語の文字と表記学びとその方法』である。