心理学コース 竹橋洋毅(教育心理学、社会心理学)
- 研究
モチベーションの心理学
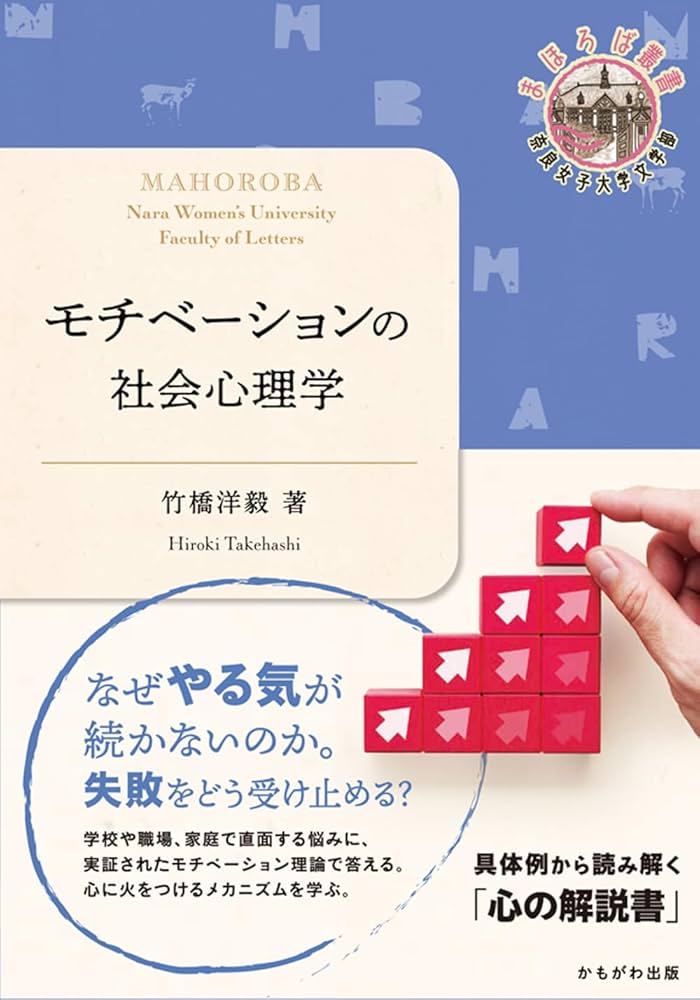
モチベーションを左右する要因とは何だろうか?こういう質問をすると、まず出てくるのが報酬や罰である。さて、実際はどうだろうか。心理学の研究によれば、報酬や罰は楽しくない活動の意欲を高める上では有効であるものの、もともと楽しかった活動では逆効果になるリスクがあり、楽しさが時に低下することが示されている(アンダーマイニング効果)。
やる気は目に見えないので、人々はその真の姿を正確に理解できていないのかもしれない。私が取り組む「モチベーション心理学」は、調査や実験によってやる気を可視化して、その仕組みを解き明かそうとする学問である。
社会的認知からのアプローチ

やる気の問題を考える上で鍵になるのは、本人の物事のとらえ方であることが膨大な研究によって示されている。あなたが一生懸命にがんばった時のことを思いだしてみてほしい。その活動は、あなたにとって重要なことで、やればできそうだと感じていたかもしれない。
逆に、あなたにとって重要でなかったり、できると思えなかったりすることだったら、やる気は下がってしまいがちである。このような本人の認識に注目して、人間行動を予測・説明しようとするのが「社会的認知」である。社会心理学の一分野であるが、教育などの問題を考える上でも非常に役立つ。
成長マインドセット
私がもっとも興味をもって研究しているのが「成長マインドセット」である。成長マインドセットは、自分の能力は生まれつきのものではなく、伸ばすことができるという信念である。
スタンフォード大学のドゥエック教授によると、マインドセットは、普段意識されないが、困難に直面したときの粘り強さに影響を及ぼすが明らかにされている。勉強、部活、仕事…人生のなかで人々は困難に直面する。困難にしなやかに対処することは、目標を達成する上でも、前向きに生きる上でも重要である。つまずいたときに「できない」ではなく、「まだできない」と考えると、気持ちが軽くなる。世界的には非常に注目されているテーマだが、日本では研究が進んでいない。だから、私が取り組んでいきたい。
学び方も大切
研究を進めていくなかで、気づいたのは「マインドセットだけではダメ」だということだ。考え方を伝えるばかりで、効果的な学び方を伝えなければ、勉強する意欲は湧かないだろう。教育心理学の研究によって、効果的な学び方(学習方略)が明らかにされている。
次の数字を覚えてほしい。「149162536496481」。丸暗記するのは難しいが、数字の意味に気づいたらすぐ覚えられて、ずっと忘れないでいられる…1~9の二乗である。意味がわかると、応用問題にも強くなる。数学でも、英語でも、社会でも。子どもの勉強の悩みを聴きながら、学び方の課題をみとり、サポートする。こんな教育実践にも取り組んでいる。
ウェルビーイングと英知

ウェルビーイングは、良く(well)あること(being)を意味し、幸せな状態のことである。幸せが重要であることは多くの人が同意すると思われるが、そこに至ることは非常に難しい。
ここまで見てきたように、モチベーションや学習の「本当に優れた方法」、英知は非常に複雑で、それらを深く理解している人はほとんどいないからである。素朴な人間理解に基づいた教育や政策を推し進めることは、不幸を招いているにもかかわらず、そのことに実施者が気づかないこともあるかもしれない。心理学は、ウェルビーイングをとらえる上で有効な枠組みを与えてくれる。